(この記事は旧サイトより移行したものです)
こんにちは こころと身体のセラピストゆうです (*^-^*)
サロン名の “和と環” も、『調和』と『循環』がテーマなのですが、私たちの身体に限った事ではなく、自然本来のありようであると思います。
私たちの日々の営みが自然の循環に則したものであり、それに寄り添っていくための視点を大切にしていく取り組みとして、今年の1月からマンションで室内コンポストを始めました。
何か始められることはないかな~と考えている方の参考になれば幸いです。
コンポストとは
コンポストというのは、枯れ葉や木の枝、そして野菜の切れ端などの生ごみなどの分解・発酵を微生物たちや菌たちの力を借りてつくる堆肥のことをいいます。
コンポスト化=堆肥化 ということです。
コンポストを作る容器のことを「コンポスター」と言いうそうですが、ここでは コンポスト ということでお伝えします。
生ごみを出さず堆肥に
普通に捨ててしまえばただのゴミですが、コンポストを使えば落ち葉や生ごも堆肥に変えていくことができるのです。
普段から野菜の皮なんかはむかずにそのままいただき、できるだけゴミにならないようにしています。
我が家はほぼベジなので、お野菜と果物がメインなので割と朝晩生ごみが発生する状況です。
それをどうにかできたらいいな~と思っていた時に、コンポストに出会うことが出来ました。
ここ数年、いろんないのちの循環について考えていたのですが、先日参加したWSでお庭と室内で実践するコンポストの話しを聴き、落ち葉も宝なんだ☆彡という氣づきもあり、まずは実践してみようと思い、木製の蓋つきのコンポストを購入。
ちなみに、参加したのは 地球守 で開催されたWSで、土壌改良や環境改善の活動をされています。 代表の高田さんは非常に尊敬できる方で、あらゆるいのちを愛ある視点でとらえており、日本のあちこちからお呼びがかかり忙しくされているのですが、本当に素晴らしい志を持たれていらっしゃるので千葉のダーチャ(土氣)で開催されるイベントなどに是非参加していただきたいです。
マンションで実践 室内コンポスト
住まいがマンションなので、コンポストを室内に置くかベランダで実践するか迷った結果、夏場に外にいるG(怖い)の存在を考え、お目にかかるのを控えたいので室内でスタートすることに。
これから室内コンポストを始めてみようかな~と検討されている方の参考になればと思います。
準備するもの

✶コンポスター(木製容器蓋つき)
✶竹炭(5ℓ)
✶もみ殻燻炭(5ℓ)
✶ピートモス(5ℓ)
✶米ぬか
✶お水
✶土嚢袋(2枚)
下準備

① 土嚢袋にピートモスを入れる

② そこに米ぬかを投入

③ もみ殻燻炭・竹炭を投入し全体的によく混ぜたあと水を加えよく混ぜる
✶ピートモス:4(5ℓ1袋使用)
✶もみ殻燻炭:1
✶米ぬか:1
✶竹炭少々
✶水
の割合で上記を土嚢袋に入れ混ぜたら、
お水も少しずつ加えベースをつくる。
※ この割合は2~3人家族を目安にしています
※ 土嚢袋は2枚重ねて使用します
果物の皮や野菜の切れ端を投入


初日の朝は、洋ナシの皮を刻んで入れベースと混ぜました。
その上に殻燻炭・米ぬかを投入したものが見えなくなるくらいを目安に振りかけて、お水も少しずつかけて全体的に混ぜて終了。
夜は野菜の切れ端を入れ、米ぬかともみ殻燻炭を振りかけからませてから全体的に混ぜる・・・というのを日々繰り返していきます。
日々、使用するのは米ぬかともみ殻燻炭で、竹炭は微調整時(時々)に使用するといった感じです。
最初は感覚や要領が掴めないかもしれませんが、なんとなくこんな感じかな~といった塩梅で、振りかける分量なども調整すれば大丈夫です。
ベースのピートモスは、少ししっとりしているくらいがといいと教えていただいたのですが、しっとり度合いもこれでいいのかな・・?と様子を見つつお水を混ぜていました。
目安はぎゅっと握った時に、程よく塊になるくらいでOKです。
お肉やお魚など動物性のものを入れても勿論大丈夫で、卵の殻は少し砕いてから入れるようにした方がいいようです。
醗酵・分解を実感ヽ(^o^)丿

何より嬉しいのがぬか床をかき混ぜるように、全体的に分解度合いなんかを確認しながら馴染ませながら下からかき混ぜてみるとき、ほんのり温かいのですよ♬
なんだか目に見えないけれど、微生物ちゃんたちが頑張ってくれていると思うと、愛おしくなりますね 💛
開始してからの一週間、朝晩野菜や果物の切れ端を投入してきましたが、まだ一番最初に入れた洋なしの皮の存在が感じられるので、新たな投入を少し控えて醗酵・分解度合いの様子を見守ってみました。
室内コンポストを始めたのが1月なので、暖房が入るとコンポストちゃんが乾燥しやすいのかなという印象です。
燻炭・米ぬか、そして、しっとり度合いが少し少なかったかなと感じたので、お水を加えて改めて全体的に混ぜて様子をみつつ水分調整をします。
時期にもよりますが混ぜるのは1日1回でも大丈夫ですが、特に醗酵が進んでるタイミングの時はコンポスト内の温度が上がる場合があるので、その時期は最低でも朝晩の2回は投入していなくても混ぜておくことをオススメします。
日々混ぜたりしながら微生物ちゃんたちとも触れ合って仲良くなって、感覚を掴んでいけますのでご安心を。
臭わないの?!

おそらく、コンポスト経験がない方は臭いが氣になると思うのですが、全く悪臭はありません。
これには私もびっくりでした。
我が家は肉は食べない半ベジライフを送っているので、割と果物の消費も多いのですね。
なので、投入する果物の皮もりんご・バナナ・パイナップル・イチゴのヘタ・ミカンやオレンジなどの柑橘系の皮・スイカの皮・ブドウの皮・・・などなど、あらゆる皮を刻んで投入していましたが、臭くなるどころかほんのりフルーティな香りがして、むしろ心地が良かったです。
フルーツの投入が少ない時期や醗酵・分解がスムーズに進んでいる時は、お土の香りがしてこちらも心地が良い感じです(*^-^*)
コンポストを初めて1年近く経ちますが、生ごみを放置しておいた時のような悪臭がしたことは1度もありませんので、匂いに関しては心配ご無用と思います。
虫は湧かないの?!
虫についても心配していましたが、今のところコバエが湧いたり虫がついたりしたことは一度もありません。
余談ですが、ベランダでプランター栽培を実践した際に、お野菜をつくるお土を購入したのですが、そのお土にはコバエやアブラムシや小さな青虫くんも発生していました(汗)
お部屋の観葉植物も、購入した観葉植物用のお土で鉢の入れ替えをした際に、コバエが大量発生したことがあったので、室内・室外関係なくその土壌の環境によって発生するようです。
虫が発生するにはそれなりの理由があるようですが、深くまで探究していませんので、明らかになったら情報をシェアしたいと思います。
注意: 水分多すぎでカビが・・・
ある日の出来事です。
いつものように果物の皮を乗せて、米糠と籾殻勲炭を振りかけて、今回は混ぜないで1日置いてみたら、こんな事になっていました💦
これはなんだ⁉️ カビかな?
カビかな?
白いフワフワしたものがびっしり生えていました。
自分で言うのもなんですが、コンポストちゃんには愛情込めて育てているのでショックでした(泣)
この白い物体は土嚢袋にも張り付いていて、袋を開けるときに、マジックテープを剥がすような音がしていたから、結構しっかりしてるみたいです。
開けるときに、ほんのり温かな感じがあったのでもしやと思い、袋の外側に触れたら温かい。
そして持ち上げてみると・・・

醗酵が進んでいるからか、横に置いていた袋や底の部分が湿っていました。。
通氣性を良くした方がいいと思ったので、横に入れていた米糠や勲炭の袋は箱から出す事にしました。
以前、参加した地球暦のイベントで知った 『 炭素循環農法 』 という農法の説明記事に、この白い物体と思われるお話しが描かれていました☆彡
✶https://www.icas.jp.net/blog/hypothesis/carbon-cycle-agricultural-methods/
説明によると、
『 白いのは糸状菌。キノコ菌など生き物がたくさんいるのが炭素循環農法の土壌です。 』
と書かれておりまして、もしかしたらこの糸状菌なのかな。。。

ハッキリとは、この白い物体の正体は分からなかったのですが、
竹炭と籾殻勲炭を少し多めに振りかけ、微生物ちゃんたちの力を信じ、
落ち葉もプラスして白い物体もろとも混ぜ混ぜする事にしました。
少し水分が多かったようです。。
微生物の凄さといのちの循環

コンポストを始めて感じたのは、やはり微生物ちゃんたちの働きって凄いなということ。
ミミズさんや土壌管理をしてくれている色んな虫さんたちにも感謝をしていましたが、微生物ちゃんたちだけでそのまま捨てればただのゴミになるものを、いのちを生み・育むお土に変えてくれるのですから凄いとしか言いようがありません。
こういった存在たちの下支えがあって、私たちは生かされているんだな~というのをしみじみ感じるのです。
環境が良いせいなのか、一緒に混ぜた種も発芽して根っこがにょきにょき伸びてくる子もいました。
分解に時間がかかったな~と感じたのは、玉ねぎの外側の茶色くなった皮です。
投入した時期も冬場だったので余計に感じたのかもしれませんが、しばらく存在感があり分解に時間がかかっている様子でした。
卵の殻なども割と時間がかかるようです。
仕上げ

コンポストの中の量がだいぶ増してきたので、投入をやめしばし醗酵・分解を見守ります。
投入した固形物がしっかり分解されているのを確認出来たら、しばし熟成・乾燥させます。
その間は、コンポストBOXの上に置き、1か月くらい寝かせた後の状態がこちら(左写真)
サラサラで、ほんのりお土の香りがします。
堆肥の活用法
出来上がった堆肥は、家庭菜園やガーデニングなどに活用できます。
私の場合、今年初挑戦したベランダでのプランター栽培時にお土に少し混ぜたり、調理の際にでたカボチャやパプリカの種などを発芽させる際にもお土に混ぜたりするなどしてみました。
お庭がある場合、植物の木の根元辺りに撒いてあげるなどで活用できます。
最後に
肥溜め農法など、その昔日本では当たり前に行われていた生活の知恵も今では見られなくなってしまいましたが、私たち日本人の生活の中には微生物たちの力による『醗酵』をうまく取り入れた文化がありました。
目には見えないけれど、私たちの腸内細菌の状態がこころや身体の健康を左右するのと同様に、自然界に存在するさまざまな微生物たちの働きによって支えられ、あらゆる循環や調和が保たれているのです。
そういったことに氣づくことが出来ると、自然界に存在するものはなに1つ無駄なものは無いし、必要だからこそ存在するのであり、それぞれの持ち場で役割があるのだなということが分かります。
これまでと同じ生活を当たり前にしてくことは、更に地球環境にダメージを与えることになるのは誰が見ても明らかです。
私たち1人ひとりが出来ることからコツコツと楽しみながら取り組まれる方が増えていくといいなぁ~と思う今日この頃です♬
木製コンポストは ▼『うるおいの森』さんにて購入
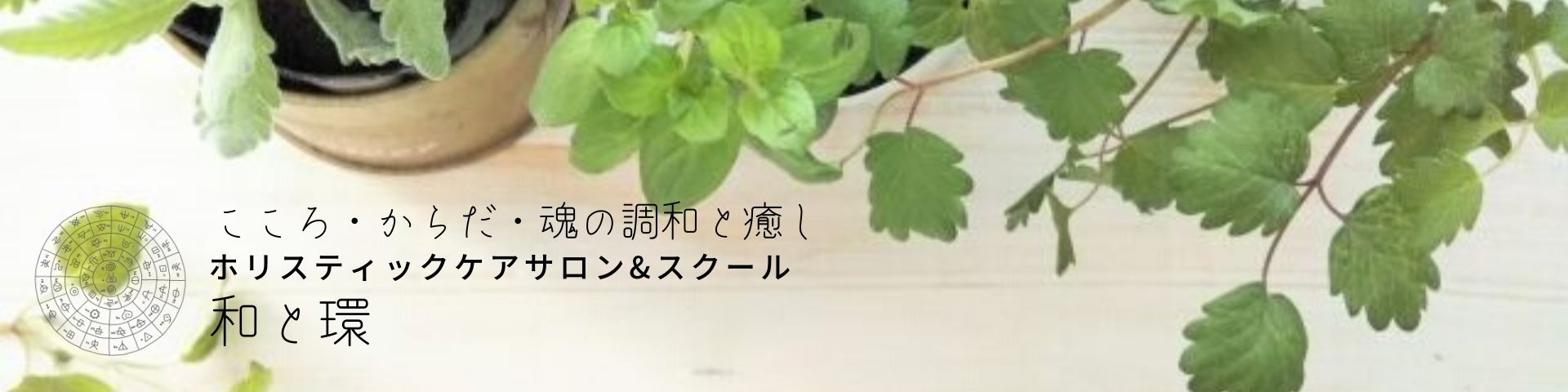





コメント